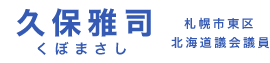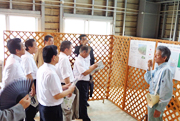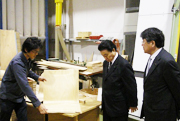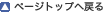��]����k�C���ցB�D�y�s���攭�i�I�v�ۉ�i�̃I�t�B�V�����E�F�u�T�C�g�ł��B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
���k�C���̐ΒY���Y �@�����̐ΒY�̐��Y�ʂ́A�������N�͔N��120���g���O��Ő��ڂ��Ă���B �@����24�N�x�̎��т͖�122���g���ŁA����͍B���@(���H�R�[���}�C��(��))����53���g���A�I���Y�̌@(���Ǝ�7��)����69���g���ƂȂ��Ă���B (�P�ʁF��g��)
��)�k�C������
���H�R�[���}�C��������Ёy���H�s�z
(2)�ΒY�̌@�����̊T�v �@���H�R�[���}�C�����̌@���Ă���ΒY�́A�s�̒��S�X����L���Vkm�ȏ�ɂ킽��C�ꉺ�ɖ����Ă���B�Y�w�͉����Ɍ����ĂT�x�`�U�x�̊ɌX�ł̂тĂ���A���̊ɂ₩�ȒY�w���Y�z�̋@�B���ɍł��K���Ă��邽�߁A���Ђ͐��E�L���̋@�B���Y�z�Ƃ��đ��Ƃ��Ă���B (3)���C�����ꎖ�Ƃɂ��� �@���Ђł͌��C���ƂƂ��āi�Ɓj�Ζ��V�R�K�X�E�����z�������@�\�iJOGMEC�j���ϑ����ꂽ�Y�Y���ΒY�̌@�E�ۈ��Z�p���x�����Ƃ����{���Ă���A�����ƃx�g�i������̌��C������Ȃ�тɗ����ւ̐��Ɣh�������{���Ă���B �@�A�W�A�Y�Y���ɂ�����I�V�x�肩��B���@��ւ̈ڍs�A�̒Y�ӏ��̍X�Ȃ�[�����E��������w�i�ɁA���{�̒Y�z���L���鍂�x�Ȑ��Y�Z�p�A�ۈ��Z�p���ړ]����u�Y�z�Z�p�ړ]�T�J�N�v��iH14�`H18�j�v�����肵�A�W���I�E�v��I�Ɏ��Ƃ����{���Ă������Ƃ��K���Ƃ��ꂽ�B �@KCM�ł͂����������Ƃ̎��{�ɂ��A���E�I�ȐΒY�����̈���Ɖ䂪���ւ̊C�O�Y�̈��苟���̊m�ۂ�}��ׂ��A�x�g�i���E�����Ȃǂ̑��荑�̃j�[�Y�f���āA�����ʓI�A�����I�Ȍ��C���Ƃ����{���Ă���A���C���̎�����אl����2,000�l����ȂǁA���荑����������]���Ă���B 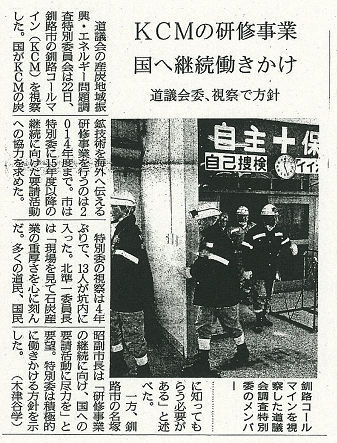 
����25�N�x�@��4���ᓹ�c��̊J���@��4���ᓹ�c��́A11��28������12��12���܂ŊJ�Â���܂����B ����ȓ��e��
�@��\�Z�̑��z�́A��ʉ�v�@226��5,100���~ �ȏ�
����25�N�x�@��3���ᓹ�c��̊J���@��3���ᓹ�c���9��10��(��)����10��4��(��)�܂ŊJ�Â������܂����B���z129��1,100���~�]�̕���25�N�x��\�Z�������܂����B���̓��e��������܂��B ����ȓ��e��
�@�����d�����Ӓn��ɂ���������ː��Ď����s�����j�^�����O�|�X�g�ɂ��āA�o�b�N�A�b�v�d���ݔ��������邱�ƂƂ��A���q�͊����S����@7,800���~�@���v�シ��ƂƂ��ɁA���q�͍ЊQ��̋��_�ƂȂ�I�t�T�C�g�Z���^�[�̈ړ]�ɗv����o��Ƃ��āA���q�͍ЊQ�ً}���ԉ��}�_�{�ݐ�����@8��1,400���~�@���v�ア�����܂����B
����25�N�x�@��2���ᓹ�c��̊J���@��2���ᓹ�c���6��18��(��)����7��5��(��)�܂ŊJ�Â������܂����B���z93��5,000���~�]�̕���25�N�x��\�Z�������܂����B
����25�N�x�@��1��k�C���c�����ň�ʎ����@��1���ᓹ�c��́A2��21������3��22���܂ŊJ�Â���܂����B   ������E���ق̎�ȓ��e��
�P�D�������N��҈���@�{�s�ɂ��� �ȏ�
����25�N�@��P��k�C���c��Վ���̊J���@�����Q�T�N�Q���V���A�����Q�T�N�@��P��k�C���c��Վ�����J�Â��܂����̂ŁA�v���܂��B ���T�v��
�@�����Q�S�N�x��\�Z�́u���{�o�ύĐ��Ɍ������ً}�o�ϑ�v�̎��{�ɔ������̕�\�Z�ȂǂɌĉ����āA
�ً}�ɑ[�u��v����o��ɂ��āA���v�̗\�Z�[�u���u���悤�Ƃ�����̂ł���A �ȏ�
�k�C���c��@�Y�Y�n��U���E�G�l���M�[��蒲�����ʈψ����
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ���� | �s���� | ������ | �T�v |
| 11��20�� | ���H�s | ���{�����i���j���H�H�� |
�@���Ђ́A�����ɂ����郌�[�������v��w�i�ɗn���p���v�̎��v���L�����Ă��邽�߁A�����̐����p�N���t�g�p���v���Y�ݔ��ł���A����������]�p����2012�N�H����n���p���v�����̎��؎������J�n���A�i�K�I�ɐ��Y���g�傷����g�݂�i�߂Ă���B �@���̂��߁A���{���̊����̃N���t�g�p���v�̘A�����������g�p�����n���p���v�̐����Ȃǂɂ��Đ���������A���^�A���@���������{�����B |
| ���H�s | (��)���H�������Y�ƋZ�p�U���Z���^�[ |
�@���Z���^�[���Ǘ��^�c��̂ƂȂ��Ă�����H�H�ƋZ�p�Z���^�[�́A�n��̃j�[�Y�ł���P���Y�Ƃ�������ۑ��؍ޓ������p�����̊��p����ю��R�G�l���M�[�H�i�n�p�������n����L�����̊��p�Ɋ֘A���錤���E�Z�p�J���⎖�Ɖ��Ɍ��������g�݂�i�߁A�����I�ȎY�Ǝx���{���W�J���Ă���B �@���̂��߁A���H�H�ƋZ�p�Z���^�[�ł̒n�撆����Ƃ̌����J���̎x���Ȃǂɂ��Đ���������A���^�A���@���������{�����B |
|
| 11��21�� | ���H�s | (��)���a�Ⓚ�v�����g |
�@���Ђ̐��X�V�X�e���́A��C�����璂�f�K�X�𒊏o�������^���܂��͊C���ɗn���������X���邱�ƂŕX�̒��̎_�f��99���ȏ��菜�����Ƃ��\�B���f�X�͂قƂ�ǎ_�f���܂܂Ȃ����߁A�_����G�ۂ̔ɐB��}�����A�N���A���ɂ����č����̂�����̐��g���n������V�N�Ȃ܂ܑS���̏���n�ɓ͂��邱�Ƃ��\�ƂȂ����B �@���̂��߁A�S�����̒��f�K�X���p�̐��X�V�X�e���̊T�v�Ȃǂɂ��Đ���������A���^�A���@���������{�����B |
| �����s | �J�l���O�F�①(��) |
�@���Ђ͍����̃t�B���[�A��g�������̍H���L���A�h�C�c�̕�@�����Ė�����őN�x���Ȃǂ̏��i���l�����߂Ă���B�܂��A�Ε�HACCP�̔F��擾���i�߁A�H�̈��S�E���S�A�ȕ։��ȂǏ���ҁA�ڋq�N�_�̐��i�Â���������B����ɕ���23�N6���ɖk�C��HACCP����q���Ǘ��F�ؐ��x�ɂ�����F���擾�����B �@���̂��߁A���i�̕t�����l����ƐH�̈��S�E���S�̎��g�݂Ȃǂɂ��Đ���������A���^�E���@���������{�����B |
|
| 11��22�� | �ʊC�s | (��)�ׂ������Ƌ��� |
�@�ʊC���̑�O�Z�N�^�[�ɂ��^�c����Ă���H�i���[�J�[�ŋ���������i�̐����̔����s���Ă���B���i�̌��ޗ���100���ʊC���Y�̐������g�p����Ă���A�q�ꂩ�琶�Y�܂ł̈�т����g���[�T�r���e�B�����A���Y�҂̊�̌����鐶���������g���A���S�ŗǎ��ȓ����i�̒��s���Ă��邱�Ƃ����А��i�̃Z�[���X�|�C���g�ƂȂ��Ă���B �@���̂��߁A�ʊC�̋������g���������i�̐����E�̔��̎��g�݂Ȃǂɂ��Đ���������A���^�A���@���������{�����B |
| ���W�� | (��)���� |
�@���Ђ́A���W�Ò���n�ՂƂ��Ĕ_�Ɠy�⌚�Ƃ��傽��Ɩ��Ƃ��ĉc��ł������A�~���Ԃ̎d�����������邽�߁A����21�N�x����V�C�^�P�̋ۏ��͔|�E�̔��ɐi�o�B�V�C�^�P�́A��Ɉ�āA�i���̗ǂ��A���������V�C�^�P��S���̊F�l�ɐH�ׂĂ������������Ƃ����z�������߂č�������Ƃ���u�z���̑��v�Ɩ��t�����Ă���B �@���̂��߁A���Ƃ���_�ƕ���i�ő��͔|�j�ւ̐i�o����Ȃǂɂ��Đ���������A���^�A���@���������{�����B |
�k�C���c��o�ψψ���@��������
�u�����Ǔ����o�ϐl�Ƃ̈ӌ�������v
�o�ȎҖ���
���@���F����24�N11��21���i���j15:00�`15:45
��@���F�k���l���𗬃Z���^�[�u�Θb���[���v
| �敪 | �E�� | ���� |
| �k�C���c�� | �o�ψψ���@�ψ� | �v�ہ@��i��4�� |
| �n����ƌo�ϒc�� | �������H��c���N���u�n�z�N���u�v | �@ |
| �@������ʊ�����Ё@��\����� | ����@���� | |
| �@�ь��ݍH�Ɗ�����Ё@��\����� | �с@�h���Y | |
| �@�L����Ђ݂��@��\����� | �e�n�@�m�� | |
| �����N��c�� | �@ | |
| �@������Ѓi�I�G�Ζ��@�햱����� | ���J�@���� | |
| �@������ЃL�^�E���R�@��\����� | �r�@�p�a | |
| �@������Д��R�َq�X�@�ꖱ����� | ���R�@�d�v | |
| �n�� �s���@�� |
�k�C�������U���ǁ@�U���ǒ� | ��t�@�� |
| �k�C�������U���ǁ@���H�J���ό��ے� | �⑺�@�H�K | |
| ���s�E�� | �k�C���o�ϕ������ہ@�ے� | ���Y�@�L |
| �k�C���o�ϕ������ہ@�卸 | ��ȁ@���F | |
| �k�C����ƋǑ����ہ@�劲 | �ڎR�@�� | |
| �k�C���c����Njc���ہ@�卸 | ����@�e�v |

����24�N�@��3��k�C���c�����̊J��
�@�k�C���c���R�����́A�X���P�P������P�O���T���܂ŊJ�Â���܂����B
�@������̋c��͕����Q�S�N�x�̓���\�Z�A����сu��Ԍ����̌��ݍĊJ�ɍR�c���A�����ӔC���ʂ����܂��悤���߂錈�c�v�A�u�k�C���ɂ����鍡�~�̓d�͎����Ɋւ���ӌ����v�Ȃǂɂ��Ăł��B
�@��\�Z�ẮA���ʂ̑[�u��v����o��Ȃǂɂ��āA���v�̗\�Z�[�u���u���悤�Ƃ�����ł���A���̑��z�́A
�@��ʉ�v�@�X�S���W�C�S�O�O���~
�@���ʉ�v�@�@�@�@�S�C�P�O�O���~
�@���@�@�v�@�X�T���Q�C�U�O�O���~�@�ƂȂ��Ă���܂��B
�@���Y�W�̎��Ɣ�Ƃ��āA���Y�Ƌ������p�{�݂̐����⋙�ƏW���̖h�Ў{�݂̐����ɑ��鏕���ȂǁA���z�T���W�C�W�O�O���~���v�ア�����܂����B
�@���ɁA�O���[���j���[�f�B�[�������ςݗ��Ă�ƂƂ��ɁA���₩�Ȏ��Ƃ̎��{��}�邱�ƂƂ��A���z�W���S�C�T�O�O���~���v�サ���ق��A���֘A�{�݂̊J�ݏ����ɗv����o���X�v�����N���[�ȂǏ��h�ݔ��̐������x�����邱�ƂƂ��A����Ջً}���������ʑƔ�@�V���T�C�R�O�O���~�@���v�ア�����܂����B
�@�܂��A�������k���̑����ɔ��������s�������������邽�߁A���ʎx���w�Z�̐������s�����ƂƂ��A�@���ʎx���w�Z�{�ݐ�����@�P���T�O�O���~�@���v�シ��ƂƂ��ɁA
�@�V���`�ɍ��ے���ւ��A�q������q�Ǝ҂ɑ��Ďx�����邱�Ƃɂ������܂����B
�@���ɁA�{�N�����������J��Z��ЊQ�Ȃǂɂ���Ў{�݂̑��������ɗv����o��Ƃ��āA�@�ЊQ������@�X���U�C�R�O�O���~�@���v�シ��ƂƂ��ɁA�{���o�ς̌��Ɋӂ݁A���̒P�Ǝ{����u���邱�ƂƂ��A���H�A�͐�Ȃǂ̓��ʑ���@�S�T���~�A�����֘A�P�Ǝ��Ɣ�@�W���~�@���v�ア�����܂����B
�@�����Ɍ�������ʉ�v�̍Γ��\�Z�̎�Ȃ��̂Ƃ������܂��ẮA
�@�@���Ɏx�o���@�@�S�T���U�C�V�O�O���~
�@�@�J�@���@���@�@�P�P���W�C�Q�O�O���~
�@�@���@�@�@�@�@�Q�R���T�C�V�O�O���~
�@�@�J�@�z�@���@�@�P�O���Q�C�T�O�O���~�@���v�ア�����܂����B
�@�k�C���O���[���j���[�f�B�[������̗L���������������悤�Ƃ�����̂ł���A�V���ɐ�����x���w�Z����ݒu���A���S�H�ƍ����w�Z��p�~����ƂƂ��ɁA�D�y�H�����w�Z�̖��̂�ύX����ق��A���������w�Z���̓��w���A�y�ѐi�����̔[�t���@��ύX���悤�Ƃ�����̂ł���܂��B
�@���H���ǍH���̍H�������_���������邱�Ƃɂ��āA�_�Ɨp�{�݂̍��Y���擾���邱�Ƃɂ��āA��������c��̋c���ɕt���ׂ��_��y�э��Y�̎擾�A���͏����Ɋւ�����̋K��ɂ��A�c���悤�Ƃ�����̂ł���܂��B
�@�����Q�R�N�x�k�C����ʉ�v�y�ѓ��ʉ�v�Γ��Ώo���Z�Ɋւ��錏�́A�n�������@�̋K��Ɋ�Â��A�c��̔F��ɕt�����̂ł���܂��B
�@�����Q�R�N�x�̖{���o�ς́A�����{��k�Ђ̉e���Ȃǂɂ��A�ˑR�Ƃ��Č������������Ă���A�����������������ɂ߂Č������ɂ��邱�Ƃ���A�u�V���ȍs�������v�̎��g�݁v�̒����Ȏ��{��}��A�{���o�ς̊������⓹�������̌���Ɏ����鏔�{������{�������܂����B
�@���̌��ʁA��ʉ�v�ɂ��܂��ẮA
�@�@�����Z�z�@�@�Q���W�C�R�V�O���R�C�Q�O�O���~
�@�@�Ώo���Z�z�@�@�Q���W�C�R�Q�T���S�C�R�O�O���~
�@�@���������@�@�@�@�@�@�@�@�S�S���W�C�X�O�O���~�@�ƂȂ�܂������A
���̂����A�J�z���Ƃ̍����ɁA
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�R�R���S�C�W�O�O���~�@���[������ƂƂ��ɁA
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�P�P���S�C�P�O�O���~�@�𗂔N�J��z�����ƂƂ������܂����B
�@���ʉ�v�ɂ��܂��ẮA
�@�@�����Z�z�@�@�T�C�T�V�S���T�C�T�O�O���~
�@�@�Ώo���Z�z�@�@�T�C�T�R�X���@�@�Q�O�O���~
�@�@���������@�@�@�@�@�@�R�T���T�C�R�O�O���~�@�ƂȂ�܂����B
�P�D�����̌��q�͔��d����~���Ă��钆�A�~���ɓd�͎��v�̃s�[�N���}����{���ɂ����āA�d�͕s���ɑ���o�ϊE�⓹���ւ̕s�����傫���L�����Ă���B���́A�ߓd���d�ɂ�铹��������Y�ƌo�ϊ����ւ̉e�����\���c��������ŁA�W�@�ւƘA�g��}��A�S�������Ė��S�ȑ�Ɏ��g�ނƂƂ��ɁA�{���ɂ�����d�͂̈��苟���Ɍ����������𑬂₩�ɐi�߂�ׂ��ł���B
�P�D�k�C���́A���R�G�l���M�[�̕�ɂł���A�ȃG�l�E�V�G�l�̎��g�݂�ϋɓI�ɐ��i���邽�߁A���́A�k�C���ȃG�l���M�[�E�V�G�l���M�[���i�s���v��ɂ�����ڕW���l�𑁋}�Ɏ����A���g�ނׂ��ł���B
�P�D�u�V���Ȗk�C���a�@���Ɖ��v�v�����v�̍���ɂ������ẮA�����a�@���ʂ����ׂ��@�\������܂��A�n���Â̈���I�E�p���I�Ȋm�ۂ�}��ƂƂ��ɁA���z�̗ݐϐԎ�������Ă��錻��A�����̈���w�ƘA�g������t�m�ۑ��f�Ñ̐��̏[���E�������͂��߁A���ޗ���̌o��̏k���ȂǁA����̌o�c���P���m���ɐ}������x�v��Ƃ��A����w�A�����������߂��v�����Ƃ��ׂ��ł���B
�P�D�S���e�n�ŁA�����߂���Ɏ��E�����Ƃ����ɂ߂Ēɂ܂������[���Ȗ�肪���₽�Ȃ��B
�����ߖ��͋ɂ߂ďd�v�ȉۑ�ł���A���̏d�含��S�Ă̋��E���͂��Ƃ�苳��W�҂��F������ƂƂ��ɁA�����ς́A���Ԃ̓I�m�Ȕc���y�і������Ɍ����Ĉ�v���͂����̐����m�����A�w�Z�A�ƒ��n��A�W�@�ւƖ��ڂȘA�g���͂̉��A�����߂̍���Ɍ����čő���̎��g�݂��s���ׂ��ł���B
�ȏ�
���Ƃ��̉āA�k�C�����̌��q�͔��d����~���A�d�͋����ɕs�������钆�A���{�ɂ�鍑���ւ̐ߓd�v�����āA�k�C���d�͊�����Ёi�ȉ��u�k�d�v�Ƃ����j�ɂ����Ă��V���̐ߓd��v���������ʁA���Ǝ{�݂⎖�Ə��Ȃǂ𒆐S�ɁA�����̗����Ƌ��͂ɂ���ĖڕW�������X���̐ߓd���}��ꂽ���Ƃ�Η͔��d���̉ғ��̑����Ȃǂɂ��v���d�ɂ͎���Ȃ������B
�@����A�ϐኦ��n�ł���{���́A�~���ɓd�͏d�v�̃s�[�N���}�����ɁA���̉ߍ��ȋC�ۏ�������A�g�[���v�Ȃǂɂ������ʂ��ēd�͂̎g�p�ʂ��������x���Ő��ڂ���Ƃ�������������A�ď�̃s�[�N���ɂ�����ߓd�Ƃ͈قȂ鍢���L���Ă���B
�@���̓~���Ԃɉߓx�Ȑߓd�v����v���d�����{���ꂽ�ꍇ�A�g�[���E�����h�~���u���̉^�]��~���l���ɂȂ��肩�˂Ȃ��d��ȉe�������O�������肩�A���Y�E�����̒�Ȃǂ̌o�ώY�Ɗ����ɂ����Ă��d��ȑ��Q�������炳��邱�ƂɂȂ�B
�@���݁A�k�d�ɂ����ẮA�����͊m�ۂɌ����āA���������V�������i��ł���Η͔��d�ݔ��̒�������̌J�艄�ׂȂǂ��s���ғ����p������ƂƂ��ɁA�ً}�ݒu�d���̒lj��ȂǁA���}���ً}�I�ȑi�߂��Ă��邪�A�Η͔��d���̌v��O��d��k�{�A�n�ݔ��̃g���u��������d�͎s�ꂩ��̍w���ʂ̕s��������z�肵���ꍇ�A���~�̓d�͎������ʂ��͔��Ɍ��������̂Ɨ\����������A���~�̐ߓd�ڕW�l�������ɐݒ肷�邩������ȏł���B
�@���̌����́A�ЂƂ��ɍ����d�͎����̌��ʂ��𖾂炩�ɂ��Ă��Ȃ�����ł���A���̂��Ƃɂ���āA�d�͕s���ɑ���o�ϊE�⓹���̕s�����傫���L�����Ă���B
�@����āA���ɂ����ẮA���~�̐��m�����k�ȓd�͎������ʂ��𑁊��ɍ쐬���A�����ɑ����m�����J�Ȑ������s���ƂƂ��ɁA�ߓx�Ȑߓd�v����v���d�̉���Ɍ����A�����ӔC�������āA�d�̗͂Z�ʂ��܂ߓd�͈��苟���̊m�ۂɖ��S�̑[�u���u����悤�������߂�B
�@�ȏ�A�n�������@��X�X���̋K��ɂ���o����B
�����Q�S�N�P�O���T��
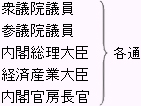
�k�C���c��c���@�� �� �� ��
�@�{�N�X���P�S���A���{�́A������ꌴ���̏d�厖�̂����P�Ƃ��āA�u�����̐V�݁E���݂͍s��Ȃ��v�Ȃǂ̌������߁A����ɂ��u2030�N��Ɍ����ғ��[���v��ڎw���Ƃ����V�����G�l���M�[����ł���u�v�V�I�G�l���M�[�E���헪�v��ł��o�����B
�@���̐헪�ɂ����āA�j�R���T�C�N�����p���Ƃ������Ƃ�u���H�ς݂̌����͐V���݂Ɋ܂߂Ȃ��v�Ƃ��鐭�{�������A�d���J���i���j�͕�����ꌴ�����̌�ɒ��f���Ă�����Ԍ����̌��ݍH�����ĊJ�����B
�@���̂��Ƃ́A���q�͋K���ψ�����肷��V���Ȉ��S���������Ă��Ȃ����Ƃ���S���ɌW��\���Ȑ������Ȃ����Ői�߂�ꂽ���̂ł���A���������G�l���M�[����Ɋւ��閾�m�ȕ������������Ȃ��������Ƃɑ傫�Ȍ�����������̂ł���B
�@��Ԍ����́A�����F�A���ؘF�ł̌����Ȃ��A�g�p�ς݊j�R�����ď������Ď��o�����v���g�j�E���ƃE�����̍����_�����i�l�n�w�R���j��S�F�S�Ŏg�p���鐢�E���̏��ƘF�ł���A�����āA���Ǝ҂̓d���J���i���j�́A����܂Ō����̉^�]�͖��o���ł��邱�Ƃ��猩�Ă��A���̈��S���̊m�ۂ�����܂ňȏ�ɋ��߂���B
�@�܂��A�k�C���̓���n��́A��Ԍ������ݗ\��n����ŒZ��23�L�����[�g����������Ă��炸�A��Ԍ����ɉߍ����̂��N����A���̉e���͂͂���m��Ȃ����̂ƂȂ邱�Ƃ���A�W�����̂�Z������́A�������O�ƕs�����\������Ă���B
�@���̂悤�Ȃ��Ƃ���A�k�C���c��́A���ɑ��A��Ԍ����̕K�v������S���ȂǂɌW�閾�m�Ȑ����Ɠ���������������܂ł̊Ԃ͌��ݍĊJ���s��Ȃ��悤���߂Ă����B����ɂ�������炸�A����d���J���i���j�͐����ӔC���ʂ������ƂȂ��A�����̎��Ԃ����������Ƃ́A��������݂ɂ�����̂ł���A�܂��ƂɈ⊶�ł���B
�@����āA�k�C���c��́A��Ԍ����̌��ݍĊJ�ɂ��čR�c����ƂƂ��ɁA���y�ѓd���J���i���j�A��Ԍ����̕K�v���y�ш��S���Ȃǂɂ��Ė��炩�ɂ��ׂ��ł���B
�@�ȏ�A���c����B
�@����24�N10��5��
�k�C���c��
�����́A���{�̃G�l���M�[���l�����Ƃ����̌��c�ɂ͎^���ł����A�̌��̎��A�ސȒv���܂����B
����24�N�@��2��k�C���c�����̊J��
�@��2��k�C���c������6��19���ɊJ���A7��6���ɕ�v���܂����̂ŁA���v���܂��B
���{��c��E���߂ăm�[�l�N�^�C��
�@�{��c����́A�N�[���r�X�̑ΏۊO�ł����B�d�͕s���̌��O������A�u�m�[�l�N�^�C�v�����ւ���ߓd������܂����B�������A�c���o�b�`��t�����㒅�̒��p�͋`���Â����܂����B
�@��\�Z�ẮA�ً}�ɑ[�u��v����o��ɂ��āA���v�̗\�Z�[�u���u���悤�Ƃ�����̂ł���A���̑��z�́A
�@�@��ʉ�v�@42��2,700���~�@�ƂȂ��Ă���܂��B
�@�{�N����������C�����J�ЊQ�Ȃǂɂ���Ў{�݂̑��������ɗv����o��Ƃ��āA
�@�@�ЊQ������@12��7,200���~�@���v�ア�����܂����B
�@�����{��k�Ђɂ���Ђ���������Ƃ̎{�݁E�ݔ��̕������Ƃɑ��Ďx�����邱�ƂƂ��A
�@�@������Ƒg���������{�ݓ��ЊQ������⏕���@9��7,700���~�@���v�シ��ƂƂ��ɁA��N11������̋L�^�I�ȍ���ɂ���Q�����_�앨�͔|�{�݂̕����̂��߁A�s�������s���������Ƃɑ��Ďx�����邱�ƂƂ��A
�@�@�_�앨�͔|�{�ݍ���ЊQ�Ɣ�⏕���@3,000���~�@���v�ア�����܂����B
�@�k�C���V�����̊J�Ƃɔ����AJR�k�C��������Ђ���o�c���������]�����u�ܗŊs�E�،Ó��v�Ԃ̕��s�ݗ����ɂ��āA��O�Z�N�^�[�ɂ��S���^�s�̊J�n�Ɍ�����������i�߂邽�߁A���v�̗\�Z�[�u���u������̂Ƃ����ق��A������̌�t����������ςݗ��Ă�ƂƂ��ɁA���₩�Ȏ��Ƃ̎��{��}�邱�ƂƂ��A�e�����֘A�o��Ƃ��āA
�@�@���z�@16��400���~�@���v�ア�����܂����B
�@�����Ɍ������Γ��\�Z�̎�Ȃ��̂Ƃ������܂��ẮA
�@�@���Ɏx�o���@18��9,000���~
�@�@�J�����@16��8,900���~�@���v�ア�����܂����B
��HAC�ւ̕⏕����
�@�����̗����q��H���̈ێ��ȂǁA������������S��������Жk�C���G�A�V�X�e�����A�������o�c�ɒ��ʂ��Ă��錻��Ɋӂ݁A����I�Ȍo�c���������邽�߂̌o�c���v���m���ɐi�߂���悤�K�v�Ȏx�����s�����Ƃ�����̂ł���܂��B
�@�����q��H���̉^�q�ɔ����o�c���S�̌y����}�邽�ߌ����⏕���x���g�[����ƂƂ��ɁA��w�̗��p���i�Ɍ��������g�݂ɑ��Ďx�����邱�ƂƂ��A���z3,200���~���v�ア�����܂����B
�@�܂��A���ʂ̎����s����������邽�߁A����24�N�x�y��25�N�x���̓��̑ݕt���ɑ��鏞�җP�\�Ȃǂ��s�����ƂƂ����ق��A�ꎞ�I�Ȏ������v�ɑΉ����ċ��Z�@�ւ��s���Z���ɑ��A2���~�����x�ɑ����⏞�����邽�߂̍����S�s�ׂ�ݒ肷�邱�ƂƂ������܂����B
����24�N7��4��
�\�Z���ʈψ���
1�D���́A�����HAC�̎��Ɖ^�c�ɂ��āA���Ƃ̒m���Ȃ���Ď��E�w�����s���ƂƂ��ɁA�A�q���A���p���A����z�Ȃǂ̐��l�����ƌv��Ǝ��Ǝ��тƂŘ������������ꍇ�ɂ́A�o�c�̂�����Ɋւ��锲�{�I�ȍČ����ɑ��₩�ɒ��肷��ׂ��ł���B
�@�@����AHAC�̌o�c��̏��ۑ�ɂ��ẮA�k�C���q��l�b�g���[�N�̊m����}��Ȃ���A���炩���߁A���܂��܂ȕ������璆�����I�Ȏ��_�ɗ����Č������s���AHAC�̌o�c���艻��}��ׂ��ł���B
�@�@�����āAHAC�̌o�c���v��i�߂�ɓ����ẮA����܂ł̌o�܂܂��A�W�����̓��ɑ��A���J�ȑΉ��ɓw�߂�悤���߂���̂ł���B
1�D���́A�n�k��Ôg�Ȃǂɑ���u�ЊQ�ɋ����܂��Â���v�Ɍ����A���i�̐��𑁋}�ɍ\�z����ƂƂ��ɁA�s������W�@�ւƘA�g���A�h�������{�݂ȂǁA�n�[�h��̋�̓I�Ȑ�����@�̌����ɑ��₩�ɒ��肷��ׂ��ł���B
�ȏ�
����24�N�x�@��1��k�C���c�����
�\�Z���ʈψ���Ŏ���
�@���́A�\�Z���ʈψ���̑�P���ȉ�Ŏw��Ǘ��Ґ��x�ɂ��āA�R���P�X�����₢�����܂����B


��@�w��Ǘ��Ґ��x�ɂ���
�i��j�����ɂ���
�����⁄
�@�w��Ǘ��҂̓����̏ɂ��Ďf���܂��B���ɂ����ẮA�n�������̖@�̉������A�����P�W�N�x����w��Ǘ��Ґ��x�����A���̌�A�����g�債���Ə��m���Ă��邪�A���݂̓����ɂ��Ďf���܂��B
�����ف�
�@���ɂ����ẮA�n�������̖@�̉������A�����P�W�N�x������̎{�݂Ɏw��Ǘ��Ґ��x�����A���̌�A�Ώێ{�݂������g�債�A���݁A���������Z���^�[�Ȃǂ̂S�U�̎{�݂ɂ����Ă��̐��x�����Ă���Ƃ���ł���܂��B
�i��j�������ʂɂ���
�����⁄
�@�S�U�{�݂œ������Ă���Ƃ̂��Ƃł��邪�A�����ɂ��ǂ̂悤�Ȍ��ʂ��������̂��f���܂��B
�����ف�
�@�w��Ǘ��Ґ��x�̓����ɔ����A���Ǝ҂̑n�ӁE�H�v�ɂ��V���Ȏ��g�݂��s���Ă���A�Ⴆ�Γ��������̈�Z���^�[���ɂ����āA��Ԃ̊J�ق�k�C���J��L�O��ٓ��ɂ����Ċe�튄�����x������ȂǁA���p�҂̃T�[�r�X����◘�p���i�Ƃ������ʂŌ��ʂ����������̂ƔF�����Ă���܂��B
�@�܂��A���x�����O�Ɣ�r���āA�Ǘ��^�c�̌�������R�X�g�̏k���̖ʂ�������ʂ��������ƍl���Ă���܂��B
�i�O�j����̌��ʂ��ɂ���
�����⁄
�@���ɂ����ẮA�w��Ǘ��Ґ��x�����Ă���{�݈ȊO�ɁA���c�̌��̎{�݂����邪�A����̎w��Ǘ��Ґ��x�̓����Ɍ��ʂ��ɂ��Ďf���܂��B
�����ف�
�@�{�N�x�̐����]���ɂ����ẮA���ƌ��C���ȂǂX�{�݂ɂ��Ďw��Ǘ��Ґ��x�̓����Ɋւ��A�ӌ���t���Ă���Ƃ���ł��邪�A�Ⴆ���ƌ��C���ɂ��ẮA���ƂɊւ��錤�C�Ƃ����Ɩ��̓��ꐫ�Ȃǂ���A�����_�ł͎��{�\�Ȓc�̂��Ȃ����ƁA
�܂��A���̑��̎{�݂ł́A�����{�݂̒��œ������ڊǗ����镔�����c������Ȃ����̂ɂ������ẮA�w��Ǘ��Ґ��x�����͈̔͂��ǂ̂悤�ɂ��邱�Ƃ��K����������K�v������ȂǁA�l�X�ȉۑ肪����Ƃ���ł���܂��B
�@����A���ꂼ��̎{�݂ɂ����āA���̓K�ۂ��܂߂Č�����i�߂Ă܂��肽���B
�i�l�j�����ɂ��I��ɂ���
�����⁄
�@�����́A�ً}�̏ꍇ����債�����\�����Ȃ������ꍇ�ȂǂɌ���Ƃ���Ă��邪�A�S�U�{�݂̂��������̎{�݂͉��{�݂������̂��A���̗��R���܂߂Ďf���܂��B
�@�܂��A������ɒ�Ă���Ă���P�R�{�݂̏ɂ��āA�����Ďf���܂��B
�����ف�
�@�����Q�P�N�x�ɂ����ẮA�s�������Ǘ�������ӎ{�݂ƈ�̓I�ɊǗ����邱�Ƃ��A�����I�Ȃ��̂Ƃ��āA�s�������w��Ǘ��҂Ƃ����{�݂��A���Θp�p�m���}�p�[�N�ȂǂT�{�݁A�܂��A���c�Z��ɂ����ẮA�w��Ǘ����s���Ă���R�V�n��̂����A������s�������A���哙���Ȃ������P�R�n��A�s�������Ǘ�������ӂ̎{�݂ƈ�̓I�ɊǗ����邱�Ƃ������I�Ȃ��̂Ƃ��āA�s�������w��Ǘ��҂Ƃ����{�݂��P�P�n��A���킹�ĂQ�S�n�悪�����ɂ��I�肳�ꂽ���̂ł���܂��B
�@���N�x�A�I����s�����P�R�{�݂ɂ����ẮA�r�����N�̐X���אڂ��鑺�c�{�݂ƈ�̓I�ȊǗ������邱�Ƃ������I�Ȃ��̂Ƃ��āA�B��A����債���Ƃ���ł���܂��B
�i�܁j�w��Ǘ��҂ɂ���
�����⁄
�@���x�����O�Ɍ����I�c�̂ȂǂɊǗ��ϑ�����Ă������̎{�݂ɂ����āA�����̈ϑ��c�̂ƌ��݂̎w��Ǘ��҂̏͂ǂ̂悤�ɂȂ��Ă���̂��A�f���܂��B
�����ف�
�@�w��Ǘ��Ґ��x�̓����O�̕����P�V�N�x�ɂ����āA���������Z���^�[���R�V�̎{�݂������I�c�̂ȂǂɊǗ��ϑ����s���Ă����Ƃ���ł���܂��B
�@���̂����A�w��Ǘ��Ґ��x������������c�̓����w��Ǘ��҂ƂȂ��Ă�����̂��A�A�C�k�����Z���^�[�ȂǂR�Q�{�݁A�V���Ȓc�̓����w��Ǘ��҂ƂȂ������̂��A����Q�P���I�̐X�ȂǂS�{�݁A�����c�̂��\�����ł���R���\�[�V�A�����w��Ǘ��҂ƂȂ������̂��A���������Z���^�[�̂P�{�݂ƂȂ��Ă���Ƃ���ł���܂��B
�i�Z�j���菑�̒��������ɂ���
�����⁄
�@���݁A����ɌW�鎖���葱���́A�w��Ǘ����Ԃ̍ŏI�N�x�̂P�O���Ɍ�����s���A�R���E�I��葱�����s���������ŁA��P�����Ɏw��c�Ă���o���A����A�c�����o�āA�N�x���ɋ��菑�̒����Ƃ�������ɂȂ��Ă���B
�@�w��Ǘ��҂���シ��ꍇ�����蓾�邱�Ƃ��l����ƁA�Ǘ��̉~���Ȉڍs�̂��߂ɂ́A���菑�̒��������𑁂߂邱�Ƃ��K�v�ƍl���邪�A�@���ł��傤���B
�����ف�
�@�w��Ǘ��҂̑I��葱���Ƃ��āA����J�n�ɕK�v�ȍ����S�s�ׂ̐ݒ�ɂ��āA�O�N�̑�R�����ŋc����������������A������s���A�P�Q���̑I��ψ���ł̐R�c�܂��A�P���ɂ͓��Ƃ��Č��҂�I�肵�A��P�����Ŏw��Ǘ��҂̎w��ɌW��c�������������A���̌�ɋ����������Ă���Ƃ���ł���܂��B
�@���������葱�������Ă���ƁA��������̓����𑁂߂邱�Ƃɂ��ẮA����ʂ����邪�A���Ƃ��ẮA�S������̋Ɩ����~���ɃX�^�[�g�ł���悤�A�I�肳�ꂽ�w��Ǘ��҂̕��X�Ə\���ȘA�g��}��Ȃ���A���i�߂Ă܂��肽���B
�i���j�w����Ԃɂ���
�����⁄
�@���ɂ�����w����Ԃ́A�{�݂̂�����Ȃnj��������K�v�Ȏ{�݈ȊO�͈ꗥ�S�N�ԂƂȂ��Ă���B���s�{���ł͂U�N�ԎႵ���͂W�N�Ԃ̎w����ԂƂ��Ă���Ƃ�������m���Ă���B
�@�{�݂̌����I�ȊǗ��A�w��Ǘ��҂��ٗp����Ă���E���̏��������l����Ǝw����Ԃ̌��������K�v�ƍl���邪�A�@���ł��傤���B
�����ف�
�@���Ƃ��ẮA�w��Ǘ��Ɩ��ɌW��T�[�r�X�̌p�����̊m�ہA�S�N���Ƃɍs���闘�p�����̌������ɘA�������v��I�ȊǗ��^�c�Ƃ������ϓ_�Ȃǂ𑍍��I�ɔ��f�������ʁA�S�N���x����{�Ƃ���w����Ԃ�ݒu�����Ƃ���ł���܂��B
�@�Ȃ��A���s�{���ɂ����ẮA�R�N����T�N���قƂ�ǂł���A�ꕔ�ɒ����Ԃ̐ݒ���s���Ă��鎖�������܂��B
�@���̎w����Ԃ́A�{�݂̖ړI�E�ԗl���Ⓑ���Ԃ̎w��ɂ�鋣���̑j�Q�Ȃǂ��l�����Ȃ���A�K�Ȋ��Ԃ�ݒ肷��K�v�����邱�Ƃ���A����A���s�{���̒����Ԑݒ�̋�̓I�ȏ�w��Ǘ��҂̈ӌ����������Ă܂��肽���B
�i���j����̑Ή��ɂ���
�����⁄
�@���Ԃ̃m�E�n�E�����p���A�����ȗ��p�T�[�r�X����邽�߂ɂ́A����̍ۂɎ����{�݂̊Ǘ����w��Ǘ��҂��s���Ɩ��̋�̓I���e�A�X�ɂ͏Z���ɒ���T�[�r�X�Ȃǎw��Ǘ��҂��B�����ׂ��ڕW���������v����������K�Ɍ������Ă����K�v������ƍl���܂��B
�@�����w��Ǘ��Ɍ����A�ǂ̂悤�Ɍ�������}���Ă����̂��f���܂��B
�����ف�
�@���ł́A�e�{�݂ɂ����āA���p�҂�ΏۂƂ��������x�������s���Ă���ق��A���p�҂���̋��E�v�]�ɂ��āA�w��Ǘ��҂������I�ɕ��A�{�݂̉~���ȊǗ��◘�p�҂ւ̃T�[�r�X�̌���ɓw�߂Ă����Ƃ���ł���܂��B
�@�����ɉ����A����̎w��Ǘ��Ґ��x�̓K�ȉ^�p��}�邽�߁A�{�݂��^�c���A���p�҂ƒ��ɐڂ��Ă���w��Ǘ��҂ƈӌ����������{���邱�Ƃ��������邱�ƂƂ��Ă���B
�@���Ƃ��ẮA�����̈ӌ����܂��A���p�҂̗����̌���ƌ����I�Ȏ{�݉^�c�Ƃ����w��Ǘ��Ґ��x�̎�|���A��蔭�������ƂƂ��ɁA���Ǝ҂����S���ċƖ������s�ł���悤�w�߂Ă܂���܂��B
��@�w��Ǘ��Ґ��x�ɂ���
���u�w��Ǘ��Ґ��x�v�́A�����P�T�N�X���Q���A�n�������@�̈ꕔ����������@���i�����P�T�N�@����W�P���B�ȉ��u�����@�v�Ƃ����B�j���{�s����A���̎{�݂̊Ǘ��Ɋւ��邱��܂ł́u�Ǘ��ϑ����x�v���������ꂽ���Ƃɂ���āA�V���ɑn�݂��ꂽ���x�ł��B
������܂ł̊Ǘ��ϑ����x�̂��Ƃł́A�n�����������̎{�݂̊Ǘ����ϑ��ł���̂́A�����O�̒n�������@�ɂ��A�����c�́i�s������y�n���Nj�Ȃǁj�A�����I�c�́i�����E�_���E������Ȃǁj�y�ю����̂��o�������O�Z�N�^�[�ȂǂɌ��肳��Ă��܂����B
���܂��A�Ǘ�����҂́A�ϑ��_��Ɋ�Â���̓I�ȊǗ��̎�����Ɩ������s���邱�Ƃ��ł��܂����A�Ǘ��̌����ƐӔC�͈��������ݒu�҂ł���n�������c�̂��L������̂ł���A�{�݂̎g�p���ȂǏ����ɊY������Ɩ��͈ϑ��ł��Ȃ����ƂƂ���Ă��܂����B
������A�w��Ǘ��Ґ��x�̂��Ƃł́A�n�������̂��w�肵���u�w��Ǘ��ҁv�ɁA�g�p�����܂ގ{�݂̊Ǘ����s�킹�邱�Ƃ��ł��܂��i�������A�g�p���̋���������s���\���ɑ��錈��ȂǁA�@�ߏ�A�n�������c�̂��邢�͒��ɐꑮ�I�ɕt�^���ꂽ�s�������͍s���܂���j�B
���]�O�̊Ǘ��ϑ����x�Ƃ͈قȂ�A�n�������c�̂͊Ǘ������̍s�g���̂�����s���܂��A�w��Ǘ��҂̊Ǘ������̍s�g�ɂ��āA�ݒu�҂Ƃ��Ă̐ӔC���ʂ������ꂩ��K�v�ɉ����Ďw�����s���A�w���ɏ]��Ȃ��ꍇ�ɂ͎w��̎�������s�����Ƃ��ł��鐧�x�ł��B
���܂��A�w��Ǘ��҂͈̔͂ɂ��Ă͖@������i�̐��Ȃ����Ƃ���A���Ԋ�Ƃ�NPO�Ȃǂ��܂ޖ@�l���̑��c�̂��A�c��̋c�����o�Ďw��Ǘ��҂Ƃ��Č��̎{�݂̊Ǘ����s�����Ƃ��\�ƂȂ�܂��B
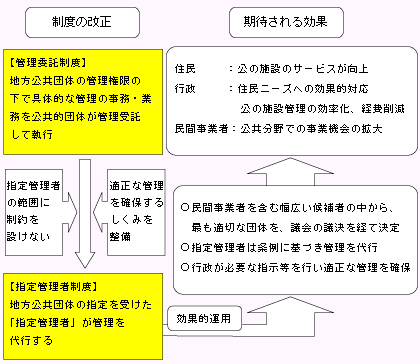
����24�N�x�@��1��k�C���c�����̊J��
�@��P��k�C���c�����͂Q���Q�R���ɊJ�Â���A�R���Q�R���ɏI���v���܂����B
�\�Z�Ă̑��z��
�@��ʉ�v�@�Q���V�C�S�O�X���X�C�P�O�O���~
�@���ʉ�v�@�@�@�T�C�R�T�U���X�C�W�O�O���~
�@���@�@�v�@�Q���Q�C�V�U�U���W�C�X�O�O���~�@�ƂȂ�܂����B
�@�������ƂƂ��āA���z�Q�C�R�T�T���S�C�V�O�O���~���v�シ��ƂƂ��ɁA�����P�Ǝ��Ɠ��Ƃ��āA���z�W�S�T���X�C�Q�O�O���~���A�܂��A�{�ݓ����ݎ��Ɣ�Ƃ��āA���z�W�V���S�C�U�O�O���~���v�サ�A�����������킹�������I�o��S�̂ŁA�R�C�Q�W�W���W�C�U�O�O���~��[�u�������܂����B
�@�������W�̎{��ɂ��܂��ẮA�h�Њ������@�ނ̐����⒡�ɂ̑ϐk���C�o��ȂǁA�h�Б�֘A�\�Z�Ƃ��āA���z�P�T���R�O�O���~���v�シ��ƂƂ��ɁA�����w�Z�̌o�c���S������}�邽�߁A
�@�@�����w�Z���Ǘ��^�c����⏕���@�Q�R�T���U�C�X�O�O���~�@���v�ア�����܂����B
�@�����������W�̎{��ɂ��܂��ẮA�������𐳏퉻�S�O���N���_�@�ɁA����Ȃ�����𗬂�[�߂邽�߁A�F�D�n��Ƃ̊W������o�ό𗬂̑��i�Ɏ��g�ނ��ƂƂ����ق��A����̑�ЊQ���ɂ����郊�X�N���\�Ȍ���ጸ���A�����\�ȎЉ���\�����Ă������߁A�{���̒n�������D�ʐ������������o�b�N�A�b�v���_�Â���𐄐i���邱�ƂƂ��A���v�̗\�Z�[�u���u���邱�ƂƂ������܂����B
�@���������W�̎{��ɂ��܂��ẮA�����J��L�O�ق̃��j���[�A���ɂ��k�C�������يJ�݂Ɍ��������g�݂𐄐i���邽�߁A
�@�k�C�������ِݒu��@�R�C�X�O�O���~�@���v�シ��ƂƂ��ɁA
�@���������ے���Ԃ̐����Ɍ����āA�����̂���Ȃ�A�C�k����ւ̗����ƋC�^������}�邽�߁A���v�̗\�Z�[�u���u���邱�ƂƂ������܂����B
�@�ی��������W�̎{��ɂ��܂��ẮA�n���Â̍Đ��Ɍ����A��Ò̐��̉ۑ�̉����Ɏ��g�ނ��ƂƂ��A
�@�@�n���ÍĐ��v�搄�i���Ɣ�@�U�P���T�C�U�O�O���~�@���v�サ���ق��A
�@�v���ғ��̍���҂�n��Ŏx���邽�߁A�����x���̏[�����ÂƉ��̘A�g�����̎��g�݂Ȃǂɂ��āA���v�̗\�Z�[�u���u���邱�ƂƂ������܂����B
�@�o�ϕ��W�̎{��ɂ��܂��ẮA�{���̓��������������ȃG�l�E�V�G�l��𐄐i���邽�߁A�n��̑��l�Ȏ�̂������E�A�g���čs���G�l���M�[�̒n�Y�n���Ɍ��������g�݂Ȃǂɑ��Ďx�����邱�ƂƂ����ق��A���A�W�A�ɂ�����H�Y�Ƃ̌����J���E�A�o���_����ڎw���u�k�C���t�[�h�E�R���v���b�N�X���ې헪��������v�\�z�̒����Ȑ��i��}�邽�߁A���v�̗\�Z�[�u���u���邱�ƂƂ������܂����B
�@�_�����W�̎{��ɂ��܂��ẮA���Y�����̕t�����l����ƒn�Y�r����}�邽�߁A�V�i��ł���u��߂�����v���g�p�������i�J���ȂǂɎ��g�ނ��ƂƂ��A
�@�@���Y�������p�]�����������Ɣ�@�P�C�O�O�O���~�@���v�ア�����܂����B
�@���Y�і����W�̎{��ɂ��܂��ẮA���Y���Y���̈��S����PR��EU�����̃z�^�e�K�C�̉q���Ǘ��̐��̊g�[�ȂǁA�C�O�̘H�̈���I�Ȉێ��E�g���}�邱�ƂƂ��A
�@�@���Y���Y���A�o�֘A�Ɣ�@�R�C�T�O�O���~�@���v�ア�����܂����B
�@���ݕ��W�̎{��ɂ��܂��ẮA�����H���̏k���Ȃǂɂ��A�������o�c���ɂ��錚�Ƃɂ��āA�{�Ƌ�����V����i�o�̎��g�݂ɑ��Ďx�����邱�ƂƂ��A
�@�@���ƌo�c�̎������Ɣ�@�T�C�U�O�O���~�@���v�ア�����܂����B
�@�x�@�{���W�̎{��ɂ��܂��ẮA���q�͊֘A�{�݂ɂ�����x���x���̐��̋�������}�邽�߁A�x�@�����Q�T�l�������邱�ƂƂ������܂����B
�@���璡�W�̎{��ɂ��܂��ẮA���ێЉ�Ŋ���ł����w�⍑�ۊ��o�ɗD�ꂽ�l�ނ��琬���邽�߁A�C���O���b�V���E�L�����v��V���ȋ���J���L�������̊J���E���H���s�����ƂƂ��A
�@�@�k�C���O���[�o���l�ވ琬���Ɣ�@�Q�C�O�O�O���~�@���v�ア�����܂����B
�@�����Ɍ�������ʉ�v�̍Γ��\�Z�̎�Ȃ��̂Ƃ������܂��ẮA
�@�@���@�@�@�Ł@�@�S�C�X�S�V���R�C�Q�O�O���~
�@�@�n����t�Ł@�@�@�@�@�@�@�@�U�C�X�X�O���~
�@�@���Ɏx�o���@�@�Q�C�X�S�O���V�C�X�O�O���~
�@�@���@���@���@�@�@�@�@�@�@�@�R�C�O�O�O���~
�@�@���@�@�@�@�@�U�C�T�Q�V���V�C�T�O�O���~�@���v�ア�����܂����B
�ȁ@��
�k�C���c��E�o�ψψ���̓��O���@����
�@�����Q�S�N�P���R�P������Q���Q���܂ł̂R���Ԃɂ킽��A�{�錧�i���s�E�Ί��s�j����ѕ��Ɍ��i�_�ˎs�j�ɂ����āA���H�J���ό�����������{���A�{�݂Ȃǂ̎��@���s���܂����̂ŁA�������܂��B




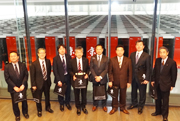

�y�P���R�P���z
�E�{�錧�Ƃ̈ӌ������i�{�錧���s�j
�@�{�錧�c��ɂ����āA��N�R���P�P���ɔ��������A�����{��k�ЂɊւ��A�k�C���o�ϕ����瓌�k�n�����ւ̖k�C���̍v���y�ѓ����o�ςւ̉e����ɂ��Đ������s���A�{�錧�o�Ϗ��H�ό������珤�H���Ǝ҂֕����x���̎��g�ݓ��ɂ��Đ����悵����A�ӌ����������{�����B
�E���̕����֘A���Ə����i�{�錧���s�j
�@�o�ϕ��̓��k�E�֓������֘A�x�����Ƌy�ыً}�Y�Ƒ����ɂ��Đ������A�����{��k�Ђ���̕����Ɋւ��鎑�ށA���i���̎��v�⒲�B��̃��X�N���U�j�[�Y�ɑ��āA��������̋������~���ɐi�߂邽�߁A���������W�E���s���ȂǁA������ƂƓ��k�E�֓��̊�ƂƂ̃}�b�`���O�𑣐i���Ă��錻�n�̎���x���R�[�f�B�l�[�^����A����܂ł̊������悵����A�ӌ����������{�����B
�y�Q���P���z
�E���H�Ɣ�Вn���@�i�{�錧���s��ы�A�Ί��s�j
�@��N�R���P�P���ɔ��������A�����{��k�Ђ̏��H��Вn�̔�Q�E�����Ȃǂɂ��Đ������A�C�݁E�͐쉈���̔�Вn������@�����B
�y�Q���Q���z
�E�_�ˈ�ÎY�Ɠs�s�i���Ɍ��_�ˎs�j
�@�_�ˎs�ł́A1998�N���A�|�[�g�A�C�����h�ɂ����Đ�[��ËZ�p�̌����J�����_�����A�Y�w���̘A�g�ɂ��A21���I�̐����Y�Ƃł����Ê֘A�Y�Ƃ̏W�ς�}��u�_�ˈ�ÎY�Ɠs�s�\�z�v�𐄐i���Ă����B
�@���݁A�u�_�ˈ�ÎY�Ɠs�s�v�ɂ́A���j�{�݂Ƃ��āA�u��[��ÃZ���^�[�v�A�u�����w�������@�����E�Đ��Ȋw���������Z���^�[�v�A�u�Տ��������Z���^�[�v�Ȃ�11�̎{�݂��ғ��A����ɁA�u�����w�������@�����R���s���[�^�u���v �v�A�u�V�����s���a�@�v�Ȃǂ̎{�݂���������Ă���B
�@�����A���E�ō����x���̌����@�ւ�A���X�Ɛi�o����200�Ђ����ƁE�c�̂̑��ݘA�g�ɂ��A���i�A�Đ���ÁA��Ë@��Ȃǂ̗Տ����p�E���p����}���Ă���B
�@�@���̂��߁A�_�ˎs�̈�ÎY�Ɗ֘A��Ƃ̗U�v�̎��g�݂Ȃǂ��A�{���̎Y�ƐU���̎Q�l�Ƃ��邽�߁A�_�ˎs��ÎY�Ɠs�s���i�{���E����������悵����A���^�A���@���������{�����B
�E�Ɨ��@�l�����w�������@�v�Z�Ȋw�����@�\�i���Ɍ��_�ˎs�j
�@�����w�������Ő�����i�߂Ă���A�X�[�p�[�R���s���[�^�u���v�́A2011�N6��20���A��26�ۃX�[�p�[�R���s���[�e�B���O��cISC�e11�i�h�C�c�E�n���u���N�J�Áj�ɂĔ��\���ꂽ�A��37��TOP500���X�g�ɂ����āA��1�ʂ��l�������B
�@����ATOP500���X�g�ɓo�^�����u���v�̃V�X�e���́A���ݐ����r���i�K�̂��̂�672➑́iCPU��68,544�j�̍\���ŁALINPACK�i�����p�b�N�j�x���`�}�[�N�ł́A���E�ō����\��8.162�y�^�t���b�v�X�i���b8,162����̕��������_���Z���j��B�����ATOP500���X�g�̎�ʂ��l�������B
�@���{�̃X�[�p�[�R���s���[�^���ATOP500���X�g�ő�1�ʂƂȂ�̂́A2004�N6���ȗ��̂��ƂƂȂ��Ă���A�{�N�H�A���p�J�n�̗\��ƂȂ��Ă���B
�@���̂��߁A�u���v�̃V�X�e���̐����⍡��̎��p���̎��g�݂Ȃǂ��A�{���̎Y�ƐU���̎Q�l�Ƃ��邽�߁A�����w�������E����������悵����A���^�A���@���������{�����B
�ȏ�